【プロ監修】屋根の雨漏り原因5選!セルフ診断や費用も解説

365日、屋根・外壁のプロがあなたの家を守ります!
雨漏り修理からリフォームまで、屋根・外壁のトラブルはBEST365にお任せください。
「適正価格」で、厳格な品質基準をクリアしたプロだけを無料でご紹介します。
| 料金 |
|
もう、悩まない。
選ばれる屋根・外壁サービス。信頼できるプロの技術を「適正価格」でご紹介します。
安心してお問い合わせください。
(このページはプロモーションが含まれています)
この記事の監修者兼ライター

徳良 仁
千葉県在住の兼業ライター。建設業界で現場経験を15年(建築3年・電気12年)経験したのち、日本最大の大手アパレルの出店開発部門で発注者としての施工監理を2年経験。現在はGAFAの1社で施設立ち上げ部門の管理職として従事。1級建築士・1級電気工事施工管理技士・第一種電気工事士も保持。日々の幸せは家族団らんを穏やかに過ごすこと。

「でも、どこから水が入ってるのか全然わからない!」
と困っていませんか?
雨漏りは、修理費用をおさえるためにも、早めに原因を見つけて対処することが肝心です。
とはいえ、雨漏りの原因を特定するのは簡単ではなく、自分で屋根の状態を確認する方法もあまり知られていません。
そのため
- 「できれば雨漏りの原因くらい、自分で確認したい」と思いつつも、どう動けばいいのか分からない方
- 誰に、いつ相談すればよいのか判断に迷ってしまう方
は多いのではないでしょうか。
この記事では、初心者にもわかりやすいよう、雨漏りのしくみや原因を丁寧に解説します。また、雨漏りを自分で特定する方法や業者の診断フローなども紹介しました。
記事を読めば、原因だけでなく、雨漏りについて「これってどうなの?」という疑問もスッキリ解決できます。
大切な住まいを守るためにも、雨漏りにはしっかり対処していきましょう。
この記事でわかること
目次
雨漏りはなぜ起こる?|仕組みと雨水の侵入経路

雨漏りは、屋根の劣化やすき間から雨水が入り込むことで発生します。屋根が正常なら、雨水は建物の外へ流れ、室内に入ることはありません。
屋根は、屋根材と防水シートの二重構造です。まずは屋根材が雨水を受け止めますが、屋根材のすき間から雨水が入り込んだとしても、その下にある防水シートが侵入を一次的に食い止める役割を担っています。
しかし、防水シートに負荷がかかり続けると徐々に劣化が進行し、やがて雨漏りに発展します。
雨水が侵入する主な経路は、次の3つです。
- 屋根材の破損・ズレ・隙間からの侵入
- 防水層(ルーフィング)の劣化・破れからの侵入
- 屋根の接合部・取り合い部(谷、棟、壁際)からの侵入

屋根の雨漏りでよくある原因【発生箇所別】

雨漏りが発生しやすい場所は、屋根の構造上おもに5つに分けられます。それぞれの箇所で劣化や破損の特徴が異なるため、原因を正しく把握することが重要です。
原因1:谷樋の詰まりや腐食

谷樋からの雨漏りのおもな原因は以下の3つです。
- 落ち葉やごみの詰まり
- 谷樋の腐食や穴が開く
- 勾配不良
谷樋は屋根面が合流する箇所で、雨水が最も集中する場所です。そのため他の部位よりも早く劣化が進み、放置すると被害が一気に進行し急拡大します。
築15年以上の住宅では、腐食が進行している場合があります。交換も視野に入れて専門業者に相談すると安心です。

原因2:棟部材の劣化や剥がれ

樋部材からの主な雨漏りの原因は以下の3つです。
- 樋板金の浮き
- 釘の緩み
- 漆喰の崩れ
棟部分は、屋根のもっとも高い部分にあるため風の影響を直接受けやすく、年間を通じて負荷がかかる場所です。そのため、いちど不具合が現れると急速に状況が悪くなります。とくに樋板金は浮き始めると飛散のリスクが高くなるため、定期的な点検が必要です。

原因3:屋根材のズレやひび割れ

屋根材は種類別に劣化パターンが異なります。以下に屋根材別の弱点と見分け方をまとめました。
| 屋根材 | 劣化開始時期の目安 | 主な劣化症状 |
| スレート屋根 | 築10〜15年 | 塗膜劣化・ひび割れ・反り・釘の緩み |
| 金属屋根 | 築15〜20年 | サビ・継ぎ目の不具合・穴開き |
| 瓦屋根 | 築20〜30年 | ズレ・割れ・漆喰の劣化 |
劣化が進んでいる場合は、“部分修理”よりも葺き替えやカバー工法などの“全面改修”の方が経済的になるケースもあります。特に築20年を超えている場合は、屋根材の交換や防水シートの張り替えも視野に入れて検討しましょう。

原因4:防水シート(ルーフィング)の劣化

防水シートの種類別の耐用年数と雨漏りのサインを一覧にしました。
| 防水シート | 耐用年数 | 雨漏りのサイン |
| アスファルトルーフィング | 10〜20年 | ・複数箇所での雨漏り発生 ・広範囲にわたる天井のシミ ・屋根裏での結露・カビ臭さ |
| 改質アスファルトルーフィング | 20〜30年 | |
| 透湿防水シート | 20〜30年 |
防水シートは、屋根材の下に設置された最後の防水層です。直接目視で確認できず、劣化すると雨漏り箇所の特定が難しくなるため、プロによる定期的な調査で早期に劣化を発見することが重要です。

原因5:取り合い板金・コーキングの劣化

取り合い部分の劣化は、進行段階によって症状が異なります。以下に段階別の特徴をまとめました。
- 初期:コーキングの軽微なひび割れ
- 中期:取り合い板金の浮き・変色
- 後期:内部腐食・雨水進入
屋根と外壁の接続部分(取り合い)は、異なる素材が接する境目のため、雨水が入りやすい場所です。劣化が進むと雨漏りを引き起こし、内部の木材が傷んだり、カビが発生しやすくなります。
見た目は軽い劣化でも、内部では深刻な傷みが進んでいることがあります。表面だけの補修では不十分なため、プロに依頼して内部まで確認してもらいましょう。

【調査データ】築何年ごろに雨漏り工事をした?

当社が実施した独自アンケートによると、雨漏りの予防や発生をきっかけに屋根工事を行ったご自宅の約半数は、築11〜30年でした。
築年数ごとのメンテナンスの目安は以下の通りです。
- 築11〜20年:塗膜や取り合い部の劣化が目立ち始める時期
- 築21〜30年:屋根材のメンテナンスや防水シートの交換が必要になる頃
屋根は見えない場所だからこそ、気づかないうちに劣化が進んでいることがあります。アンケート結果からもわかるように、築10年を過ぎたら、いちど専門業者に点検を依頼すると安心です。
いますぐ確認!雨漏りの前兆をセルフチェック

雨漏りには3つの前兆サインがあります。早期に発見すれば大がかりな修理にはならず、修理費を抑えられます。

壁や天井のシミ

室内のシミは雨漏りの最も分かりやすいサインです。たとえば以下のような場所に現れたシミには、それぞれ異なる原因が考えられます。
- 窓まわりの壁
- 天井の隅
- エアコン周辺
- クローゼットや押入れ内の壁面のシミ
窓まわりの壁のシミは、サッシのコーキングや防水シートの劣化が原因です。外壁の防水性能が落ちているサインといえるでしょう。
また天井の隅にシミができている場合は、屋根の棟板金の浮きや、防水層の破れなどが考えられます。
いっぽう、エアコンのまわりにシミがある場合は、配管の貫通部分にできたわずかな隙間から雨水が侵入している場合が多いです。とくに風を伴う雨の日に悪化しやすい傾向があります。
クローゼットや押入れの奥にできたシミは、外壁からの浸水が壁の中を伝って、目につきにくい場所まで回り込んでいる状態かもしれません。気づいたときには、すでに雨漏りが進行しているケースも多いです。
シミからみる雨漏りの緊急度
シミの大きさや色から緊急度を判定する目安を以下にまとめました。
| シミの大きさ | シミの色 | 緊急度 |
| 直径5cm未満 | 薄茶色 | 低 |
| 直径5-15cm | 濃茶色 | 中 |
| 直径15cm以上 | 黒色 | 高 |

カビ臭

雨の後にいつもよりカビ臭が強くなったら、それは隠れた雨漏りのサインかもしれません。カビは放置すると急速に広がっていくため、早めに対処しておくと安心です。
以下のエリアは、カビ臭が発生しやすいので、日頃からとくに気にかけておきましょう。
- 最上階天井(屋根からの雨漏り)
- 北側居室(乾燥しにくい)
- 押入れ・物入(空気の流れが悪い)
カビ臭の特徴から見る雨漏りの緊急度
カビ臭の強さや持続性によって、雨漏りの進行度や緊急性をある程度見極めることができます。以下に基準をまとめています。
| カビ臭の特徴 | 可能性 | 緊急度 |
| 雨の後のみ臭い | 高 | 中 |
| 常時臭い・換気で改善しない | 高 | 高 |
| 土臭い・腐敗臭 | 極めて高 | 極めて高 |
>> 参考:カビによる健康障害(独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所)

水滴や湿気

雨の後に感じる異常な湿気は、雨漏りのサインである可能性もあります。結露と異なり、湿気は雨漏りの最も早い段階で現れる症状です。一般的な結露と雨漏りによる水滴や湿り気の見分け方を以下にまとめました。
| 項 目 | 一般的な結露 | 雨漏りによる水滴や湿気 |
| 発生タイミング | 朝方・冬季 | 雨天・雨の後 |
| 発生場所 | 窓周辺 | 局所的・不規則 |
| 継続性 | 季節限定的 | 雨のたびに発生 |

【セルフ調査】自分で雨漏り原因を調査する方法

雨漏りの原因は、セルフ調査でも特定できる場合もあります。
被害箇所や原因をある程度特定することで、その後の専門業者への相談がスムーズになったり、不要な工事を避けられたりするのがメリットです。
ここでは、セルフ調査の方法について詳しく解説します。

調査に必要な道具

適切な道具を準備できれば、調査の精度を向上することができます。必須となる道具と、あると便利な道具を以下にまとめました。
| 優 先 度 | 道 具 | 用 途 |
| 必須道具 | 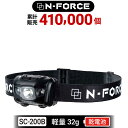 LEDヘッドライト |
暗所での詳細確認 |
 デジタルカメラ・スマホ |
記録・証拠保全 | |
 メジャー |
被害範囲の測定 | |
 マスキングテープ |
マーキング・目印 | |
| あると便利な道具 |  双眼鏡 |
屋根の詳細確認 |
 デジタル湿度計 |
湿度異常の検出 | |
 脚立(1.8m以下) |
安全な高所確認 |

目視検査のポイント

目視検査をおこなうときは、確認項目と内容を決めておきましょう。「どの場所に、どのような異変があるか」を整理しておけば、専門業者に依頼する際の説明が的確になり、調査・修理もスムーズです。
以下に、室内・屋外それぞれの確認項目をまとめました。
●室内の確認項目
| 場所 | 確認する内容 |
| 天井全体 | シミ・変色・膨らみ |
| 壁面(特に上部) | 水染み・カビ・クロスの剥がれ |
| 窓周辺 | サッシ回り・カーテンの湿り |
| 電気設備周辺 | コンセント・照明器具の異常 |
●室外の確認項目
| 場所 | 確認する内容 |
| 屋根全体 | ズレ・ひび割れ・色褪せ |
| 雨樋・谷樋 | 詰まり・変形・錆 |
| 棟部分 | 板金の浮き・漆喰の崩れ |
| 外壁取り合い部 | コーキング・板金の状態 |

散水検査の手順とコツ

散水検査は、雨漏りの原因を効果的に特定できる方法です。ただし、誤ったやり方は誤診や建物の損傷につながるため、必ず正しい手順で行いましょう。
以下に、散水試験の実施条件と手順をまとめました。
| 散水検査の実施判断条件 | 判 定 | 理 由 |
| 雨漏り箇所が特定済み | 実施可能 | 原因箇所確定 |
| 原因箇所が不明 | 専門業者推奨 | 誤診断リスク高 |
| 電気設備に近接している | 実施禁止 | 感電・漏電の危険 |
| 2階以上の高所 | 実施禁止 | 転落事故のリスク |
| 安全な散水検査の手順 |
|

セルフ調査の落とし穴

セルフ調査には、2つの大きな落とし穴があります。
なかでも安全面のリスクは深刻で、毎年、調査中の転落事故が多数発生しています。セルフ調査による事故も増加傾向にあるため、安全で正確な調査のためにリスクを正しく理解しておきましょう。
誤診断で工事費がかさむ

素人判断で原因を誤ると、無駄な工事が増え、結果的に費用が大きく膨らみます。よくある誤診断パターンと、そのリスクをまとめました。
よくある誤診断パターン
- 表面的な症状だけで原因を特定する
- 複数箇所の雨漏りを単一の原因と決めつける
- 応急処置で根本原因を見逃す
誤診断によるリスク
- 不要な工事で費用が増える
- 根本原因が放置され被害が拡大する
- 再発し、追加の工事費用がかかる
実際にあった誤診断の事例も以下にまとめています。
| 誤診断事例 | 実際の原因 | 費用差 |
| 瓦のズレ | 防水シートの劣化 | 10万円 → 80万円 |
| コーキングの劣化 | 谷樋の腐食 | 5万円 → 30万円 |
| 防水シートの部分補修 | 全面改修が必要 | 20万円 → 150万円 |
雨漏りの原因を見誤ると、手戻りや追加工事で費用が何十万円も膨らむことがあります。

転落事故につながりやすい

人は「少しだけなら」と油断して、本来避けるべき行動をとってしまうことがあります。屋根に上る、脚立を不安定に使うといった危険な行動も例外ではありません。
筆者も現場経験の中でいくつかの転落事故と遭遇しましたが、ほとんどが当事者のちょっとした気の緩みが原因です。「自分は大丈夫」と思わず、常に危険が潜んでいることを必ず意識してください。
以下に事故が起きやすい状況と事故事例をまとめました。
事故が起きやすい状況
- 雨上がりの濡れた屋根での作業(足が滑り転落)
- 一人での調査作業(いざという時、助けを呼べず重症化)
- 脚立や椅子の上で、背伸びや手を伸ばすような作業(バランスを崩し転落)

【プロ調査】専門業者の診断フローと費用相場

専門業者に見てもらえば、原因を的確に突き止めてもらえ、状況に合った修理方法を提案してもらえます。
この章では調査を依頼する場合の条件や流れを解説します。
雨漏り調査の費用相場と無料診断の条件

雨漏りの調査は、方法によって費用や調査精度に差があります。まずは、どの方法が適しているのかを知っておくことが大切です。
下記に、専門業者が行う調査の種類や費用相場、所要時間の目安をまとめました。
| 調査方法 | 費用相場(目安) | 所要時間(目安) | 調査精度 |
| 目視調査 | 無料〜1万円 | 30分〜1時間程度 | 低〜中 |
| 散水調査 | 3〜10万円 | 2時間〜半日程度 | 中〜高 |
| 赤外線調査 | 10〜20万円 | 1時間〜2時間程度 | 高 |
| 発光液調査 | 15〜30万円 | 半日〜1日程度 | 最高 |
無料診断は目視による簡易な確認が中心ですが、プロが見ることでおおよその原因や修理の方向性がわかります。まずは気軽に調査・診断を相談してみましょう。
ただし、正確な原因特定や報告書の作成が必要な場合は、有料調査を前提に考えた方が確実です。

調査の流れ

雨漏り調査を業者に依頼する際は、「調査内容」と「調査後の報告書の有無」を事前に確認することが重要です。報告書がなければ、修理後のトラブルや追加費用の原因になりかねません。
以下に、専門業者による標準的な調査フローをまとめました。業者選びの参考にしてください。
| ヒアリング (15分程度) |
・雨漏り発生状況の確認 ・過去の修理歴の把握 ・建物の基本情報収集 |
| 目視調査 (30分~1時間程度) |
・室内の被害状況確認 ・屋外からの屋根点検 ・周辺環境の調査 |
| 詳細調査 (必要に応じて) |
・散水・赤外線調査等 ・屋根裏・床下の確認 ・原因箇所の特定 |
| 報告書作成 (1週間以内) |
・調査結果のまとめ ・修理方針の提案 ・費用見積もりの提示 |

雨漏りの原因別|屋根の修理方法と費用早見表
「どんな修理が必要で、いくらかかるのか分からない…」という方のために、雨漏りの原因別に修理内容と費用を整理しました。
| 原因 | 修理方法 | 費用の目安 |
| 谷樋の詰まりや腐食 | 谷樋清掃または板金交換・補修 | 3~15万円 |
| 棟部材の劣化や剥がれ | 棟板金の交換・貫板の補強 | 5~20万円 |
| 屋根材のズレやひび割れ | 屋根材の補修・交換 | 3~10万円 |
| 防水シートの劣化 | 防水シートの張り替え(部分または全面) | 10万円~ |
| 取り合い板金・コーキングの劣化 | 板金の補修・コーキングの再施工 | 3~10万円 |
雨漏りは原因によって対処法も大きく変わるため、安易な自己判断は禁物です。気になる症状があれば、専門業者に点検を依頼するのが安心です。
365日、屋根・外壁のプロがあなたの家を守ります!
雨漏り修理からリフォームまで、屋根・外壁のトラブルはBEST365にお任せください。
「適正価格」で、厳格な品質基準をクリアしたプロだけを無料でご紹介します。
| 料金 |
|
もう、悩まない。
選ばれる屋根・外壁サービス。信頼できるプロの技術を「適正価格」でご紹介します。
安心してお問い合わせください。
【注意!】雨漏り放置のリスク

雨漏りは、放置すればするほど被害が拡大します。
| 放置期間 | 想定される修理費用 | 想定される修理範囲 |
| 発見直後 | 5万円〜50万円 | 漏水の原因部分のみ |
| 3ヶ月後 | 20万円〜100万円 | 上記 + 内装仕上げ部材 |
| 6ヶ月後 | 50万円〜300万円 | 上記 + 内装下地部材 |
| 1年後 | 100万円〜500万円 | 上記 + 主要な構造部材 |
本記事では、放置によって起こる二次被害(建物・健康・火災)のリスクと、それを避けるために今すぐできる対策をプロ目線で詳しく解説します。

建物構造へのダメージ・資産価値の低下

構造部材が傷むと住み続けるリスクだけでなく資産価値も下がります。
| 構造への影響 | ・木材の腐食:耐震性低下 ・金属部材の錆:強度低下 ・断熱材の劣化:断熱・防音性の低下 |
| 資産価値への影響 | ・不動産査定額の大幅減少 ・売却時の大幅な値下げ ・修繕履歴による評価低下 |

カビや害虫の発生

雨漏りを放置すれば、カビや害虫が発生し、健康被害や建物の劣化につながります。特にシロアリは、構造部材を食い荒らして家の強度を著しく低下させるため、早めの対処が必要です。
| 健康への影響 | ・アレルギー症状の悪化 ・呼吸器疾患のリスク増加 ・子供や高齢者への特に深刻な影響 |
| 害虫による問題 | ・シロアリの発生・増殖 ・ゴキブリ等の害虫の住み着き ・ダニの大量発生 |

漏電・火災リスク

雨漏りで電気系統が濡れると、漏電による火災や感電のリスクが高まります。分電盤の安全装置が働けばブレーカーで遮断されますが、もともと水のかかる想定をしていない回路には安全装置が付いていない場合が多いです。
| 電気系統への影響 | ・配線の劣化による漏電や感電 ・ブレーカーの誤作動 ・電気機器の故障 |
| 火災のリスク | ・漏電による出火 ・電気系統のショート |

まとめ|迷ったらすぐ相談。それがコスト削減と安心への近道

本記事では屋根からの雨漏りの原因やセルフ調査の方法、修理費用について解説しました。
セルフ調査はあくまで参考程度にとどめ、迷ったらすぐプロに相談することが、余計な出費や被害拡大を防ぐ一番の近道です。
今すぐできる!雨漏り原因の特定のポイント
- 天井や壁のシミ・カビ臭などの症状と場所を記録する
- 屋根や谷樋、棟板金、取り合い部の劣化を目視で確認する
- 築15年以上なら屋根や防水シートの劣化を疑う
- 雨の後に湿り気やカビ臭が続く場所は前兆と考える
- 無料診断を賢く利用し、早めにプロに相談する

屋根からの雨漏りの原因でよくある質問
築年数と雨漏り原因にはどんな関係がありますか?
築年数により雨漏りの主な原因が変わります。築15年を境に雨漏り発生率が急上昇するため、定期点検の検討しましょう。
火災保険で雨漏り修理はできますか?
台風や強風など自然災害が原因の雨漏りであれば、火災保険の適用できる場合があります。ただし、経年劣化による雨漏りは対象外となります。
365日、屋根・外壁のプロがあなたの家を守ります!
雨漏り修理からリフォームまで、屋根・外壁のトラブルはBEST365にお任せください。
「適正価格」で、厳格な品質基準をクリアしたプロだけを無料でご紹介します。
| 料金 |
|
もう、悩まない。
選ばれる屋根・外壁サービス。信頼できるプロの技術を「適正価格」でご紹介します。
安心してお問い合わせください。
この記事の監修者兼ライター

徳良 仁
千葉県在住の兼業ライター。建設業界で現場経験を15年(建築3年・電気12年)経験したのち、日本最大の大手アパレルの出店開発部門で発注者としての施工監理を2年経験。現在はGAFAの1社で施設立ち上げ部門の管理職として従事。1級建築士・1級電気工事施工管理技士・第一種電気工事士も保持。日々の幸せは家族団らんを穏やかに過ごすこと。
ご相談の流れ
電話から問い合わせ
相談無料受付時間 8:00~19:00
050-3528-1955

STEP 1
電話

STEP 2
コールセンターにてヒヤリング

STEP 3
相談内容に応じてプロが対応





